皆さんは、東京書籍の「NEW ACTION LEGEND -思考と戦略-」をご存じですか?
実は、網羅系といわれる参考書シリーズの一つなのですが、「チャート式」のほうが有名かもしれません。そのため「ニューアクション レジェンド?」となった人がいるかもしれません。
ですが、本書は非常に素晴らしい参考書です。特に、東京書籍の教科書を使っている場合、教科書との相性は本当に抜群です。
今回は、『NEW ACTION LEGEND -思考と戦略-』がどのような参考書なのかについて見ていきます。 より自分に合った参考書を選ぶことができるように、そして、手にした参考書を完成させることができるように、参考にしてみてください。
数学力向上に必要な姿勢
あなたは、問題をただ解けばそれで数学の勉強になると思っていませんか?
しかしそれは、「あらゆるパターンの問題を丸暗記して解けるようにする」という事ことです。「入試問題が解けるかどうか」が「それまでにその問題を見たことがあるどうか」で決まるとも言えます。しかし、入試本番でこれまでに見たのとまったく同じ問題が出ることはほぼあり得ません。という事は、この方法では合格点を取ることはできないという事になります。
これを防ぐために大事なことは、『1を聞いて10を知ろうとする姿勢』です。言い換えると、一つ一つの問題からきちんと一般的な法則を見つけ、それらを体系化・整理することが大事ということになります。 要は、「良い道具をそろえて、使い方をきちんと理解・整理しておこう」ということです。
NEW ACTION LEGEND -思考と戦略-とは




〈おすすめ度:★★★★☆〉
出版社:東京書籍
サイズ:A5判
NEW ACTION LEGENDの概要
NEW ACTIONシリーズ(LEGEND、FRONTIERの2段階)ののうち、ハイレベルな方の参考書です。青チヤートやFocus Goldなどが同レベル帯の参考書になっています。きちんと完成させれば、全統記述模試(河合塾)での偏差値70が目指せるイメージです。 このレベル帯の網羅系参考書としては、「知識の理解・定着が浅い人に最もおすすめ」ですが、改定を重ねるごとに青チヤートやFocus Goldが追い付いてきています
NEW ACTION LEGENDの構成
本体構成
- 〔例題集〕例題の問題文をまとめた小冊子。解答を見てしまう心配なく例題に挑戦できるようになっています。
- 〔例題MAP〕例題、コラムの関連性を視覚化し、全体像をイメージしながら学習が進められるようになっています。
- 〔例題一覧〕その節で出てくる例題の一覧表です。
- 〔まとめ〕用語・低利・公式などがコンパクトにまとまっています。
- 〔例題ページ〕本書のメインになるページです。
- 〔コラム〕重要事項の詳しい解説や、やや発展的な内容について説明されています。
- 〔問題編〕節末にまとめられた、例題と同レベルの類題です。
- 〔本質を問う〕例題で扱った内容について、「なぜ」を考える練習をするための問題です。
- 〔Let’s Try!〕入試の標準レベルの問題に挑戦できます。
- 〔思考の戦略編〕対称性、実験、一般化などを紹介し、初見の問題への対応力が鍛えられるようになっています。
- 〔入試攻略〕難関大学の典型レベルの問題に挑戦できます。
例題ページの構成

問題数と難易度設定
問題数
文系:ⅠAⅡB / 理系:ⅠAⅡBⅢC を目安として参考にしてください。
実際には、文系は数学Cの内容のうち、ベクトルに取り組む必要があるのでもう少し増えることになります。

難易度
- ★☆☆☆:教科書の例~例題レベル
- ★★☆☆:教科書章末~入試基礎レベル
- ★★★☆:上位国公立大学やGMARCH・関関同立レベルの大学入試での典型問題レベル
- ★★★★:旧帝大・早慶など難関大学の入試での典型問題レベル
- 入試攻略:最難関大学の入試での基礎レベル
★×2までのマスターで、全統記述の偏差値の目安がおおよそ55です。ほかの参考書でいうと、『基礎問題精講』を仕上げたときと同程度の到達レベルといえます。
★×4までのマスターで『標準問題精講』や『青チャートの例題(コンパス5つまで)』を仕上げたときと同程度の到達レベルになります。全統記述の偏差値の目安はおおよそ65です。
入試攻略まで仕上げることができれば、東大・京大などの最難関にもくらいつけるようになります。ただし、本書に限らず、網羅系の参考書だけでこのレベルを仕上げるのは非効率でおすすめできません。
NEW ACTION LEGENDの特徴
必要十分な問題ラインナップ
『Focus Gold』や『青チャート』だと、典型パターン(定石)として習得しておくべきレベルを超えた問題が一定数含まれます。
それに対して、本書では絶妙なラインを狙った問題選定となっており、ほとんどの大学で数学の合格点を狙える素晴らしいレベル設定になっています。
充実のコラム
「Play Back」「Go Ahead」という2種類の形式のコラムが存在します。
会話形式で補足的内容、あるいは発展的内容が紹介されているので必ず目を通しましょう。
また、「探求例題」「チャレンジ」という問題を伴っていることもあります。これらは、Focus Goldなどでは例題として扱われているタイプの問題なので、忘れずに取り組むことが必要です。
「思考のプロセス」が丁寧
どのように考えてその問題を解くか、が例題ごとに記載されています。
数学は、問題を見たときにどういった思考をして答えを導いたらいいのかを知ることはとても重要です。ここが丁寧なのは非常にありがたいポイントです。
別冊の例題集
例題の解答が目に入ってしまうという人のため、問題だけをピックアップした別冊がついています。
これは、周回時などに非常に便利です。
例題MAP
各章はじめに例題ごとの関係性をマッピングしたページがあります。
NEW ACTION LEGENDの使い方
ここでは、初めて実施するとき(1周目)と2周目以降に分けて、本書の進め方と注意点について説明していきます。
1周目の流れ
1周目の流れは次のようになります。インプットを丁寧に行うことが1周目のメインの目的です。
- 例題(赤・黒・探求)・チャレンジを解く
まずは例題が解けるかトライします。
解けたら◯(=復習しなくていい意味の印)をつけてください。このとき、解説を確認し、抜けている知識や勘違いがないかのチェックは絶対に行うようにしましょう。
間違えたり、解き方がわからなかったりという場合には、すぐに×(=復習すべきという意味の印)をつけ、解説を熟読しましょう。
1周目は、新しい解き方や考え方を増やすために解いていきます。知識がない状態で長い時間をかけて考えても効率が悪いだけです。少し考えてみて分からなければ、すぐに解説を確認し、解法を習得することを優先しましょう。このときに、「〜という式(文言)があったら、〜をする」というif-thenの形でインプットするように意識し、応用性を高めることも大切です。 - 例題下の練習を解く
例題でインプットした知識が身についているかを確認します。
例題できちんと知識をインプットできていれば、例題が解けなくても、練習は解けるはずです。
例題と同じように、解けたら◯、間違えたり、解き方がわからなかったら×をつけましょう。 例題には×がつき、練習には◯がつく問題が多いはずです。そういった問題は、2周目では例題だけやればOKなので、復習(周回)の効率がとても高くなります。 - 節末の問題を解く
例題、練習の両方に〇が付いた場合には、節末の問題に挑戦してみてください。これも正解できるようなら2周目以降で自信をもってとばせます!
1周目はほとんどの問題ができないはずです。これは誰でも(東大合格者であっても)同じなので気にしてはいけません。そもそも新しい解き方を身につけるために勉強しているのですから、1周目から解けなくて当たり前です。
「この問題」を解くための知識は、言い換えると丸暗記です。これでは、応用性が低く、貴重な記憶容量の無駄使いです。1つの問題を通して応用性の高い知識を見つけ出すことは簡単ではないですが、「このタイプの問題が出たらこう解いたらいいのでは?」と、自分なりに攻略法を見つけるようにしてください。
わからない問題が出てきたときに、解説を読みながら30分悩んでも理解できないというばあいには、それ以上時間をかけてもその時点で理解できるようにはなりません。より基本的な内容の参考に戻ったり、次の周回に回したりといった対応をとるようにしましょう。何度か繰り返している過程で解けるようになります。
2周目以降
2周目以降の目的は知識の定着と実戦力を高めることです。知識の定着を最優先に取り組んでください。
- 前の周回のときに×のついた例題、練習・チャレンジを解く
1周目と同様に、例題→練習・チャレンジの順に解き進めていきましょう。
このとき、すでに〇のついているものについてはサッと確認するだけ(3周目以降は完全に飛ばす)でかまいません。
また、2周目以降では節末の”問題”については解く必要はありません。周回速度を優先させたほうがメリットは大きいです。 - 各節の節末にある「本質を問う」「Let’s try」を解く
7~8割の例題、練習に解答できるようになった章については、「本質を問う」「Let’s try」を解いてみてください。
このとき、本番での時間を意識し、大問1つにつき20分以内と決めて取り組むのが重要です。この段階まで来れた人は、時間に対する意識も高める必要があります。 - 思考の戦略編に進む
ⅠA/ⅡB/Ⅲ/Cのそれぞれで、一通りの範囲が学習出来たら、各学習範囲の「思考の戦略編」に進みましょう。
導入を読んだ後、解説ページを見ずに戦略例題に取り組んだうえで、〇×をつけ練習に取り組むというこれまでと同じ流れをここでも行ってください。
NEW ACTION LEGENDを進める目的は、入試で必要になる基本解法パターンの習得です。入試で初見の問題に対応できるかどうかは、「このタイプの問題が出たらこう解いたらいい」と、自分なりの攻略法を組み合わせることができるかどうかで決まります。そのための第1段階が、基本的な問題で「なぜそう解き進めるのか」を説明できることです。答えが合うこと以上に、解法がきちんと説明できることを意識するようにしましょう。
どんな人に NEW ACTION LEGEND はおすすめ?
NEW ACTION LEGENDは、同レベル帯の網羅系参考書と比べて取り組みやすい参考書です。ですが、やはり一定以上の基礎知識は必要です。そのため、教科書内容はある程度(完璧でなくても構いません)仕上がっている、難関大学への合格を目指す人におすすめといえます。
特に、学校で使っている教科書が東京書籍の場合には、非常に相性がよいので、ぜひ活用してほしいと思います。
一方で、網羅系の宿命として、問題数が多い=仕上げるのにある程度の時間が必要という面があるのも事実です。そのため、本番までの時間が少ない人が手を出すのは危険です。
また、すでに『Focus Gold』『青チャート』『総合的研究』などを使用しているのであれば、わざわざ乗り換える必要はありません。
NEW ACTION LEGENDの後にやるべき参考書は?
最後に、NEW ACTION LEGENDが仕上がったら、何を進めていくべきかについて、志望校別に例を紹介します。
上位国公立大学・GMARCH・関関同立レベルの私立大学を目指すという人
文系数学-重要事項完全習得編-と文系数学-重要事項完全習得編-に取り組んでください(理系の人は数学Ⅲ-重要事項完全習得編-にも取り組んでください)。
国公立大学志望の人は、上記に加えて 国公立標準問題集 Can Pass にも取り組んでみましょう。これらを通して、実際にアウトプットする力を鍛えたらあとは過去問へ進むだけです。
東大・京大などの難関大学を目指す人
大学への数学 1対1対応の演習で入試の典型レベルの解法パターンをさらに増やしていきましょう。
その後さらに、大学への数学 新スタンダード演習(通称:スタ演)に進むことで、最難関大学への対応力を磨き上げてください。
ここまで出来たら、東大の過去問であっても怖くないはずです。





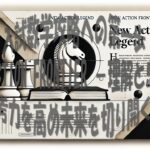
コメント